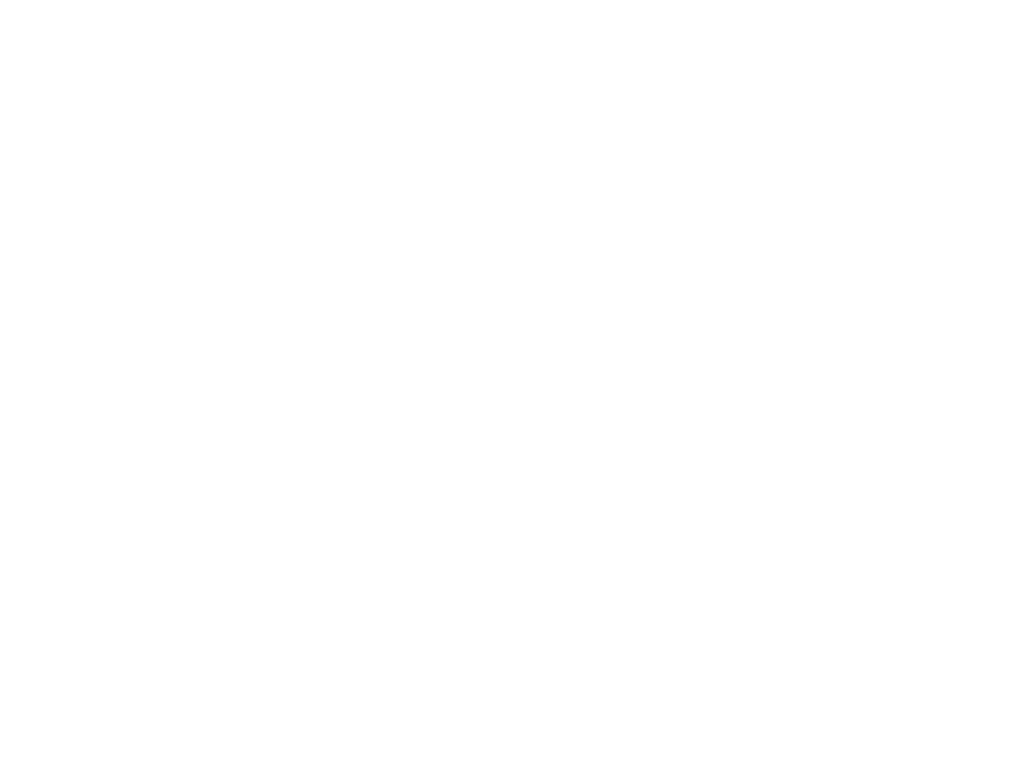フランスの作曲家モーリス・ラヴェルの生誕150周年を記念して、昨年からパリでは彼の代表曲とも言える《ボレロ》を題した展覧会が開催中だ。ラヴェルや《ボレロ》に聞き覚えがなくとも、その音楽を耳にしたことがある人は多いのではないか。1928年に作曲されて以来、世界中で演奏され続けている古典作品の一つである。
大胆に表現することが許されるなら、《ボレロ》は1つの主題が1つの大きなクレッシェンドとともに何度も繰り返される、非常にシンプルな作品である。正確には2つの主題が順番に繰り返されているのだが、その2つの主題が、雪だるまを作るようにくるくると回りながら拡大していくのだ。それだけとも言えるのだが、この作品の魅力はその簡潔さとは対照的に私たちにいくつもの面を見せてくれる。
今回は展覧会をレポートするとともに《ボレロ》の一つの側面と考える官能性について焦点を当ててみたいと思う。
展覧会の概要
会場に入るとまず《ボレロ》の演奏を映像で鑑賞するところから始まる。2023年にパリ管弦楽団による演奏が収録されたもので、若き指揮者クラウス・マケラ1が監督を務めた。音楽を視覚装置を使って表現するという印象的な試みである。
ステージでは、中心にいる指揮者を囲むように螺旋形にオーケストラが並ぶ。全員を見渡すため指揮者はゆっくりと回る台の上に立つ。
今回、視覚装置として使用されたのは「リズム」「メロディー(旋律)」「オスティナート(繰り返し)」を表す3つの光だった。《ボレロ》はこの3つで構成されている曲だからだ。演奏者のそばにはライトがありそれぞれの構成部を演奏している間はその色が光る。
例えば終盤に向かいながら光が増えていく様は視覚にも聴覚にも迫ってくるし、3つの光が楽譜の役割となり、作品の理解への一助にもなっている。この新しい試みにより、私たち鑑賞者はまさに音を目で見て楽しむことができる。本文章の終わりに映像が視聴できる情報を記載する。(下図:執筆者による作成で、光の並び方は一例である)

その後は作曲家の略歴とともに《ボレロ》が他の芸術作品、例えば映画やダンスなど多様な作品に用いられてきたことが紹介されている。一部を挙げると、モーリス・ベジャール振付のバレエや、園子温監督の『愛のむきだし』(2009)では戦闘場面に使用されていた。また、作曲家自身の人柄について彼の趣味嗜好や両親との関係に触れながら展覧会は終わる。19世紀末に開かれたパリ万博では欧州圏外の文化が紹介され、当時多くの芸術家にオリエンタリスムの影響がみられる。ラヴェルもまた例外にもれず、日本のオブジェなどを収集していた。スペインのバスク地方出身の母親との愛情深い関係からスペインに関連する作品をいくつも残した。自動車産業の分野でエンジニアの父親が残した緻密な設計図は、息子のラヴェルの楽譜にも色濃く現れているようだ。
特筆すべきは、視覚化された演奏の種明かしをするように、本展覧会に関わった専門家によって音楽構造が紐解かれていることだ。光で表現された3つの役割が1枚の図で説明されている。ここではグラフを用いて縦軸に「リズム」「メロディー (旋律)」「オスティナート(繰り返し)」の3つが展開されている。オスティナートは主題に付随しているので、第一主題または第二主題の繰り返しが何回目なのかが読み取れる。横軸で展開されるのは各楽器パートである。最初はリズムを担うスネアドラムとメロディーを奏でるフルートの独奏から始まり、作品が進むごとに楽器が変わりながら少しずつ追加されていく。グラフが右に向かうほど縦軸に楽器の名前が増えていくことがわかる。このように図式化された楽譜には音符はないが、その図を見れば《ボレロ》であるとわかるほど簡潔にまとめられている。つまり、音楽的知識や楽譜が読めることは関係がない。2
音楽の官能性と踊り
本展覧会でも紹介されているように、ラヴェルの作曲に両親の影響が現れているのは自然なことだろう。その代表とも言えるのが今回の《ボレロ》であるわけだが、情熱溢れるスペインの舞踊音楽に、「繰り返し」の機械的要素が加えられることで逆説的に官能性が引き立っているように思われる。時計の秒針や一定に動く工場の機械のごとく常に繰り返されるメロディーは、音の増幅により高揚感が高まっていく。
踊りは伝統的に男女の関係を取り持つ働きをしていることもあり容易に誘惑と結びつく。村の男女が初めて触れ合う場所には踊りがあったし、サロメも彼女の得意な踊りでヘロデ王を魅了した。
止まることなく繰り返される音はピストンの機械運動を連想させ、そのイメージはボレロのリズムとメロディーに乗ってより扇情的になる。これがラヴェルの魔術的な魅力ではないだろうか。音楽の官能性をここで見る。
展覧会の感想
絵画の展覧会と異なり、提示するものに制限がある音楽は、今回のように作曲家の生誕にかけないとなかなか展覧会をみる機会は少ない。一般に「クラシック音楽」と日本語で括られている分野はどうしても敷居が高いように思われる。日本のコンサート会場で見かける年齢層には若干の偏りが見られる。今回《ボレロ》の展覧会に訪れていたのは幅広い世代の人だった。フランス国民の音楽に対する距離感も当然考えられるが、いかにこの作品が人々に聴かれているかということも大きいだろう。およそ100年前に書かれた《ボレロ》が今後の100年でどのような汎用性を持つのか心が高鳴る。
おまけ:ラヴェルの生きた時代ベル・エポック
ラヴェルが活躍した19世紀から20世紀初頭、特に後者の時期をフランスでは「ベル・エポックBelle époque(美しき時代)」と呼ぶ。作曲家だけではなく作家、詩人、画家、彫刻家、歌手、ダンサーなどあらゆる芸術家たちがパリに集い、まさに芸術が交じり合い繁栄した美しい時代である。 この時期、特に音楽はロシアからやってきたプロデューサー、ディアギレフ3の活躍によりバレエとの関わりが強くなる。ラヴェルの《ダフニスとクロエ》(1912)、ドビュッシーの《ペレアスとメリザンド》(1898)、ストラヴィンスキーの《春の祭典》(1913)、またピカソが衣装や舞台装置を担当したサティの《パラード》(1917)などあらゆるバレエ曲が花開いた。
フィルハーモニー・ド・パリの公式サイト引用サイト
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/27890-ravel-bolero
今展覧会のURL
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/27890-ravel-bolero
今展覧会で紹介された演奏(演奏は50分52秒から開始)
https://philharmoniedeparis.fr/fr/live/documentaire-creation/1178536-ravel-en-mille-eclats
- クラウス・マケラ Klaus Mäkelä フィンランド出身の指揮者、チェリスト。2021年からパリ管弦楽団で音楽監督を務めている。 ↩︎
- voir RAVEL BOLÉRO, sous la direction d’ouvrage Lucie Kayas, Jean-François Cornu, Paris, éditions de La Martinière, 2024, p.187-189 ↩︎
- セルゲイ・ディアギレフ( Sergei Diaghilev 1872-1929)
バレエ・リュス(ロシアバレエ団)の創設者であり、名高い興行師であった。彼の活躍によりこの楽団は世界各地で公演を行った。 ↩︎